受付時間 | 9:30~18:30(土日祝祭日は除く) |
|---|
電話番号 | 03-5577-7320 |
|---|
最新法律トピック
「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(平成28年12月14日)
2016年12月14日、公正取引委員会は、中小事業者の取引条件の改善を図る観点から、下請法・独占禁止法の一層の運用強化に向けた取組みの一環として、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正しました。
この改正は違法とされる行為の対象を拡大するものではなく、違反行為事例を現行の66事例から141事例へ大幅に増加させることにより、下請法に対する具体的な理解を広めるためのものです。
概要
●主な内容
本改正では、公正取引委員会による勧告・指導の中で、繰り返し見受けられた行為、事業者が問題ないと認識しやすい行為等が追加されています。追加された違反行為事例の中には、以下のようなものがあります。
1.支払制度に起因する支払遅延
親事業者は、自動車部品の製造を下請事業者に委託しているところ、毎月二五日納品締切、翌々月五日支払の支払制度を採っているため、下請事業者の給付を受領してから六〇日を超えて下請代金を支払っていた。
2.下請代金を据え置くことによる買いたたき
親事業者は、親事業者から下請事業者に対して使用することを指定した原材料の価格や燃料費、電気料金といったエネルギーコスト、労務費等のコストが高騰していることが明らかな状況において、下請事業者から従来の単価のままでは対応できないとして単価の引上げの求めがあったにもかかわらず、下請事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定めた。
3.下請代金の額から一定額を差し引くことによる減額
コンビニエンスストア本部である親事業者は、消費者に販売する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ、店舗において値引きセールを実施することを理由に、下請代金から一定額を差し引いて支払った。
4.不当なやり直し
親事業者は、アニメーションの動画の作成を下請事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ、親事業者が内容確認の上、完成品を受領したにもかかわらず、プロデューサーの意向により動画の品質を引き上げるための作業を行わせ、それに伴い生じた追加の費用を負担しなかった。
まとめ
下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける方は、改正された下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準を一度お読みいただければと思います。そして、下請法遵守に向けた体制整備及び下請取引の条件の再検討をしていただければと思います。内容の詳細につきましては、公正取引委員会のサイトをご参照いただければと思います。
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正(平成29年6月16日)
2017年6月16日、公正取引委員会は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(以下、「本ガイドライン」といいます。)を改正しました。わかりやすさの観点から全体の構成を見直すとともに、最近の流通・取引実態に照らした修正や具体例の追加などが行われています。
概要
●主な内容
1.構成の変更
本ガイドラインの中で似たような行為類型に関する記載が一本化されるとともに、過去に違反や相談事例が存在しない行為類型などの記載が削除されています。
他方、近年事例が多い、いわゆる抱き合わせ販売に関する項目が追加されています。
2.垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準の考え方の明確化
垂直的制限行為とは、事業者が、取引先事業者の販売価格、取扱商品、販売地域、取引先等の制限を行う行為をいい、契約によって制限をする場合のほか、事業者が直接又は間接に要請することなどにより事実上制限する場合も含まれます。
垂直的制限行為は、公正な競争を阻害するおそれがある場合には違法と判断されますが、本ガイドラインでは、以下のように、公正な競争を阻害するおそれの有無の判断に際しての考慮要素が具体化されました。
① ブランド間競争の状況
② ブランド内競争の状況
③ 事業者の市場における地位
④ 取引先事業者の事業活動に及ぼす影響
⑤ 取引先事業者の数及び市場における地位
3.オンライン取引に関する垂直的制限行為についての留意点の説明等の追加
近年の電子取引の拡大をふまえ、いわゆるプラットフォーム事業者に関する留意点の説明等が追加されています。具体的には、以下の記載が新たに明記されました。
①インターネットを利用した取引か実店舗における取引かで基本的な考え方を異にするものではない旨。
②プラットフォーム事業者による垂直的制限行為についても、実店舗の場合と基本的な考え方は同じであり、その適法・違法性判断に当たっての考慮事項として、ネットワーク効果を踏まえた市場における地位等も含まれる旨。
まとめ
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」につきましては、あらゆる業種で問題となりうるため、必要に応じて事業内容や契約等の確認をしていただければと思います。詳細につきましては、公正取引委員会のサイトをご参照いただければと思います。
「民法の一部を改正する法律」の成立・公布(平成29年6月2日)、「消費者契約法の一部を改正する法律」の施行(平成29年6月3日)
2017年5月26日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、同年6月2日に公布されました。また、2017年6月3日、「消費者契約法の一部を改正する法律」が施行されました。
概要
≪民法の一部を改正する法律案≫
①定型約款に関し、定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなされますが、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効とすることを明記するとともに、定型約款を準備した者が取引の相手方の同意を得ることなく定型約款の内容を一方的に変更するための要件等が整備されます。
②消滅時効について、短期消滅時効の特例をいずれも廃止するとともに、消滅時効の期間について、原則として権利行使が可能であることを知った時から五年に統一するなど、時効に関する規定の整備が行われます。
③法定利率について、現行の年五パーセントから年三パーセントに引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する制度が導入されます。
≪消費者契約法の一部を改正する法律≫
①消費者の解除権を放棄させる条項の無効(第8条の2)
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権や、消費者契約が有償契約の場合である場合において、当該消費契約の目的物に隠れた瑕疵があること等により生じた消費者の解除権を放棄させる条項の無効が規定されました。
②第10条に例示を追加
第10条に「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」との文言が追加されました。消費者契約法10条の「公の秩序に関しない規定」には、「明文の規定のみならず、一般的な法理論等も含まれる」と判示した最高裁判例(平成23年7月15日判決民集65巻5号2269頁)を踏まえて、そのような契約条項の例示として意思表示擬制条項が追加されました。
まとめ
「民法の一部を改正する法律」及び「消費者契約法の一部を改正する法律」では、消費者に重点を置いた変更がなされています。「民法の一部を改正する法律」については、2020年をめどに施行されますが、「消費者契約法の一部を改正する法律」は既に施行されているため、消費者向けのサービスを取り扱っている方は、規約や契約等の見直しをしていただければと思います。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)」の公表(平成28年11月30日)
2016年11月30日、個人情報保護委員会は、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)」を公表しました。通則編及び匿名加工情報編については、平成29年3月31日に改正がなされました。016
概要
改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されますが、それに先立ち、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」が公表されています。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の主な内容としましては、従来、関係省庁が作成していたガイドラインのうち、個人情報保護法に関するものにつき、平成27年改正の施行(平成29年5月30日)をもって、原則として「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に一元化するというものです。
ただし、医療関連・金融関連・情報通信関連分野等については、個人情報の性質及び利用方法並びに従来の規律の特殊性を踏まえて、個人情報保護委員会が作成したガイドラインを基礎としつつ、追加的に、当該分野においてさらに必要となるガイドライン等が定められます。そこで、企業としてはこれらも遵守する必要があります。また、認定個人情報保護団体の対象事業者は、当該団体が作成する個人情報保護指針を遵守することも必要になります。
まとめ
近年、経済活動のグローバル化の進展や新たなIT技術を用いたサービスの展開により、我が国の個人情報保護法制を取り巻く状況は絶えず変化しています。このような状況の中で、企業には、より一層、個人情報の適正な取扱いが求められます。
皆様には、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」をご確認いただき、皆様が関わる分野につきましては、追加的なガイドライン等もご確認いただければと存じます。また、認定個人情報保護団体の対象となる方は、当該団体が作成する個人情報指針もご確認いただきたいと存じます。
具体的な改正の内容の詳細につきましては、個人情報保護委員会のホームページをご参照いただければと存じます。
「割賦販売法の一部を改正する法律」の公布(平成28年12月9日)
2016年12月9日、「割賦販売法の一部を改正する法律」が平成28年法律第99号として公布されました。
本法律の趣旨
近年、クレジットカードを取り扱う販売業者におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加しています。また、カード発行を行う会社と販売業者と契約を締結する会社が別会社となる形態が増加し、これに伴ってクレジットカードを取り扱う販売業者の管理が行き届かないケースも出てきています。こうした状況を踏まえ、革新的な金融サービス事業を行う FinTech(フィンテック、Finance×Technology の略。)企業の決済代行業への参入を見据えつつ、安全・安心なクレジットカード利用環境を実現するための必要な措置を講じるものです。また、本措置は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、インバウンド需要を取り込むことにも資するものです。
概要
(1)クレジットカード情報の適切な管理等
販売業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止(決済端末のIC対応化等)を義務付けます。
(2)販売業者に対する管理強化
クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者に登録制度を設け、その契約を締結した販売業者に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うことなどを義務付けます。
(3)FinTech の更なる参入を見据えた環境整備
①十分な体制を有する FinTech 企業も(2)の登録を受け、法的位置付けを獲得することを可能とします。
②カード利用時の販売業者の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とします。
(4)特定商取引法(「特商法」)の改正(2016年6月)に対応するための措置
特商法の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権等が拡充されたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約について、割賦販売法においても同様の措置を講じます。
まとめ
割賦販売法の一部を改正する法律案は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。消費者向けのサービスを行っている方は、クレジットカード番号等の取扱いについて注意をして頂ければと思います。法律の内容の詳細につきましては、経済産業省のサイトを御覧頂ければと思います。
2016年10月1日、「消費者の財産的損害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「消費者集団訴訟特例法」といいます)が施行されました。
改正の概要
①消費者集団訟特例法は、消費者契約に関して多数の消費者に生じた財産的損害を集団的に回復するための裁判手続を創設する法律です。特定適格消費者団体(平成28年11月現在全国14団体)が消費者に代わって事業者に対して訴えを提起します。
②二段階型の訴訟制度
- 一段階目の手続では事業者の共通義務の確認が行われます。これにより、事業者が消費者に対して共通して金銭を支払う義務があると判断されれば二段階目に審理が進みます。
- 二段階目の手続では個別の消費者に対する債権額を確定します。確定した債権額に従い、事業者は消費者に対して金銭を支払うことになります。
③対象となる請求(第3条第1項)
- 契約上の債務の履行の請求(第1号)
- 不当利得に係る請求(第2号)
- 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求(第3号)
- 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求(第4号)
- 不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求(第5号)
まとめ
消費者向けのサービスを行っているクライアント様は被害回復裁判手続への対応を検討して頂ければと思います。法律の内容の詳細につきましては、消費者庁のサイトを御覧頂ければと思います。
2016年6月3日、経済産業省は、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂を発表しました。
改正の概要
インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法律問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要なことといえます。そのため、経済産業省は、平成14年3月から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表し、随時改訂を行っています。この6月、ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、改訂が行われました。
具体的な改定内容の例として、①未成年者による意思表示、②ユーザー間取引、③ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任、④インターネット上の著作物の利用等が一部改訂されています。また、新規論点の追加として、データ消失時の顧客に対する法的責任の基本的な考え方が示されています。
まとめ
近年、インターネットを巡る新たな法律問題が噴出しており、電子商取引をされている事業者様は、準則等の改訂や今後の動向に注視が必要となります。具体的な改訂項目の内容の詳細につきましては、経済産業省のサイトをご参照頂ければと思います。
2016年5月27日、公正取引委員会は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正を発表しました。
改正の概要
生産財・資本財の取引と消費財の流通取引における垂直的制限行為に関して、本ガイドラインにおいて示されている「一定の基準や要件を満たす場合に、原則、法令違反に問われることがないとされる範囲」いわゆる「セーフ・ハーバー」基準が改正されています。
改正前では、「市場における有力な事業者」とは、市場シェア10%以上又は上位3位以内であることが一応の目安とされ、市場シェア10%未満、かつ、上位4位以下である事業者が特定の非価格制限行為を行う場合には、通常、市場閉鎖や価格維持のおそれはなく、違法とはならないとされていました。これに対して、「市場シェア10%未満」という範囲は狭すぎではないかなどの批判があったことから、セーフ・ハーバーの市場シェア基準の水準を10%から20%に引き上げ、順位基準を廃止する改正がなされました。したがって、第1位の事業者であっても、市場シェアが20%以下であればセーフ・ハーバーの対象となります。
なお、再販売価格維持行為や流通業者の取引先の制限及び小売業者の販売方法の制限については、セーフ・ハーバーの適用対象とはなっておりませんので、ご留意いただければと思います。
まとめ
公正取引委員会は、本年2月に「流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会」を設置しており、本ガイドラインの更なる改正を進めることが見込まれていますので、今後の動向に注視が必要となります。詳細につきましては、公正取引委員会のサイトをご参照頂ければと思います。
- 1特定商取引法
 悪質事業者への対応として、業務停止命令の期間の伸長(最長1年⇒2年)、また、行政調査に関する権限や刑事罰の強化がされました。
悪質事業者への対応として、業務停止命令の期間の伸長(最長1年⇒2年)、また、行政調査に関する権限や刑事罰の強化がされました。 違反事業者の所在が不明な場合に、諸文書を交付する旨を一定期間提示することにより事業者に交付されたものとみなし(公示送達により)処分を可能としました。
違反事業者の所在が不明な場合に、諸文書を交付する旨を一定期間提示することにより事業者に交付されたものとみなし(公示送達により)処分を可能としました。 業務停止命令を受けた悪質事業者に対し、消費者利益を保護するために必要な措置を指示できることとした行政処分規定が設けられました。
業務停止命令を受けた悪質事業者に対し、消費者利益を保護するために必要な措置を指示できることとした行政処分規定が設けられました。 電話勧誘販売における過量販売規制が導入されました(訪問販売ルールの拡張)。
電話勧誘販売における過量販売規制が導入されました(訪問販売ルールの拡張)。
- 2消費者契約法
 契約締結過程に係る規律
契約締結過程に係る規律
・過量な内容の消費者契約の取消しができるとし、改正前にはなかった新たな取消権が規定されました。
・不実告知による取消しの対象となる重要事項の範囲が拡大されました(「消費者の生命、身体、財産等についての損害又は危険を回避するための通常必要と判断される事情」を追加)。
・取消権の行使期間について、改正前は、「追認することができる時から6カ月」となっていたところ、「1年」に伸長されました。 契約条項の内容に係る規律
契約条項の内容に係る規律
・無効となる消費者契約の条項の類型が追加されました。
⇒事業者の債務不履行の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項 等
まとめ
改正法の公布日(2016年6月3日)から改正消費者契約法は1年以内、改正特定商取引法は1年6ヶ月以内に施行されますので、消費者向けのサービスを取り扱っている企業様は、規約や契約等の見直しをしていただければと思います。
近年、企業の秘密情報の流出事件が相次ぐ中、企業にとって秘密情報の保護強化が喫緊の課題であるとして、経済産業省は、平成28年2月に「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」を公表しました。
ハンドブックの概要
ハンドブックでは、秘密情報を把握・評価し、秘密としたいものを決定する際の考え方、具体的な漏えい防止対策、取引先などの秘密情報の侵害防止策、万が一情報漏えいが起こってしまった場合の対応方法等が紹介されており、また、「情報漏えい対策一覧」、「各種契約書等の参考例」、及び「競業避止義務契約の有効性について」などの参考資料もあります。
<自社の秘密情報の漏えい対策>
- 保有する情報をどのように洗い出し、その情報をどのように評価するのか
- 秘密として保持する情報と、そうでない情報を分ける際の考え方
- 情報漏えい対策は、闇雲に実施するのでは非効率。犯罪額を参考に誰を対象とし、どのようなことを目的とするかに整理して対策を紹介
〔5つの「対策の目的」〕
①秘密情報に「近寄りにくくする」…アクセス権の限定、施錠管理
②秘密情報の「持出しを困難にする」…私物USB等の利用禁止
③漏えいが「見つかりやすい環境づくり」…レイアウトの工夫、防犯カメラの設置
④「秘密情報と思わなかったという事態を避ける」…マル秘表示、ルール周知
⑤社員の「やる気を高める」…ワークライフバランス、社内コミュニケーション
<他社から訴えられないために>
- 保有する情報は、自社の独自情報と立証できるようにしておく
- 転職者の受入れ、共同研究開発など、他社とのトラブルが起きやすい場面ごとに対応策を紹介…前職での契約関係の確認、他社情報の分離保管など
<情報漏えいが発生した場合の対応>
- 情報漏えいの兆候をいち早く把握するための留意点
- 情報漏えいが確認された時の初動対応…社内調査、証拠保全
まとめ
社内規則等の定めにより、従業者の職務発明について会社に原始帰属させることをお考えの企業様は、特許庁から公表予定の「改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)」に照らし合わせて、社内規則等を定める必要があります。
詳細につきましては、特許庁のHPをご参照ください。
特許法の改正(施行日:平成28年4月1日)
特許法が改正され、平成28年4月1日から施行されます。今回の改正によって、職務発明制度が見直されることになります。
※職務発明制度とは、従業者等が職務上行った発明(職務発明)について、使用者等が取得した場合の権利やその対価(報酬)の取扱いについて定める制度です。
職務発明制度の見直し
- 1見直し前
 特許を受ける権利は発明者である従業者に帰属し、使用者が特許出願するには、その権利を譲り受ける形となっています。
特許を受ける権利は発明者である従業者に帰属し、使用者が特許出願するには、その権利を譲り受ける形となっています。 発明者である従業者は、特許を受ける権利を使用者に承継させた場合、その対価を請求することができます。
発明者である従業者は、特許を受ける権利を使用者に承継させた場合、その対価を請求することができます。
- 2見直し後
 使用者が、職務発明について、使用者に特許を受ける権利を取得させる旨をあらかじめ社内規則等に定めたときは、その特許を受ける権利は、職務発明が発生した時から使用者に帰属します。他方で、あらかじめ社内規則等で職務発明の帰属について定めていない場合には、特許を受ける権利は発明者である従業者に帰属します。
使用者が、職務発明について、使用者に特許を受ける権利を取得させる旨をあらかじめ社内規則等に定めたときは、その特許を受ける権利は、職務発明が発生した時から使用者に帰属します。他方で、あらかじめ社内規則等で職務発明の帰属について定めていない場合には、特許を受ける権利は発明者である従業者に帰属します。 発明者である従業者が、特許を受ける権利を使用者に取得させた場合、従業者は、使用者から相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有します。
発明者である従業者が、特許を受ける権利を使用者に取得させた場合、従業者は、使用者から相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有します。 職務発明に係る規則等や従業者が使用者から受ける経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針が特許庁から公表されます。
職務発明に係る規則等や従業者が使用者から受ける経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針が特許庁から公表されます。
まとめ
社内規則等の定めにより、従業者の職務発明について会社に原始帰属させることをお考えの企業様は、特許庁から公表予定の「改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)」に照らし合わせて、社内規則等を定める必要があります。
詳細につきましては、特許庁のHPをご参照ください。
- 1刑事上・民事上の保護範囲の拡大
・営業秘密の転得者処罰範囲の拡大
最初の不正開示者から開示を受けた者(2次取得者)以降の者から不正開示を受けた者(3次取得者以降の者)の不正使用・不正開示行為を処罰対象に追加
・未遂行為を処罰対象に追加
・営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制
他人の営業秘密の不正使用により生産した製品の譲渡・輸出入等の禁止
・国外犯処罰の範囲拡大
海外サーバー(クラウドなど)等に保管された営業秘密を海外において不正取得する行為を処罰対象とすることを明確化
- 2罰則の強化等による抑止力の向上・罰金刑の上限の引き上げ(海外における不正使用など一定の場合に重罰化)
・営業秘密侵害罪を非親告罪化
・任意的没収規定(営業秘密侵害罪により生じた犯罪収益を裁判所の判断により没収することができる規定)の導入
- 3民事救済の実効性の向上
・損害賠償請求等の容易化(立証負担の軽減)
・営業秘密の不正使用に対する差止請求の期間制限を延長(10年⇒20年)
まとめ
今回の改正によって、営業秘密の保護が強化されることとなりますので、これを機に、企業内における営業秘密の管理方法の見直しや従業員に対する情報漏えいリスクの周知徹底が必要になると思います。また、経済産業省が公表している「営業秘密管理指針(平成27年1月全部改訂)」では、参考裁判例を取り上げながら、営業秘密の管理方法について指針が示されていますので、ご参照いただければと思います。
- 1不当勧誘規制における見直し 不当勧誘規制では、消費者は、不適切な勧誘(重要事項についての不実告知・不利益事実の不告知、断定的判断の提供、不退去、監禁)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができるとされています。
中間とりまとめでは、今までの消費者トラブルや裁判例等を踏まえて、「勧誘」概念の見直し(※)や事業者と委託関係がない第三者による不当勧誘行為も対象にするなどして規制対象範囲を拡張する方針を示しています。
※不当勧誘規制の要件である「勧誘」の概念について、今まで規制対象外とされていた不特定の者に向けられた広告等(テレビ、新聞、インターネット上の広告等)も「勧誘」に含まれる広い概念に改めることが検討されています。
- 2不当条項規制における見直し 不当条項規制では、消費者は、消費者に一方的に不当・不利益な契約条項について、無効を主張することができるとされています。
中間とりまとめでは、解除権・解約権の放棄・制限条項などの不当条項の類型を追加することや条項の有効性に関する立証責任についての見直し(※)も検討されています。
※現在、契約条項の不当性は消費者が立証すべきものであるところ、事業者が条項の有効性を立証しなければならないことに変更される可能性があります。
まとめ
今回の見直しは、上記の他にも事業者の実務に大きな影響を与える論点が多く取り上げられており、専門調査会には、日本経済団体連合会をはじめとする事業者側からの反対意見が寄せられている状況です。早ければ来年の通常国会に改正法案として提出される見通しとなっておりますので、今後の動向に注意が必要です。
- 1個人情報の定義の明確化(身体的特徴等が該当)を図り、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、病歴等が含まれる個人情報(要配慮個人情報)に関する規定を整備しています。
- 2特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したもの(匿名加工情報)に関する加工方法や取扱い等、また、個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定を整備しています。
- 3トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)し、不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪を新設しています。
- 4個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化します。
- 5国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定や外国にある第三者への個人データの提供に関する規定を整備しています。
その他の改正事項として、本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の厳格化や利用目的の制限の緩和、また、取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者へも個人情報保護法を適用させることなどが挙げられます。
まとめ
先般の日本年金機構の情報漏えい事件が発生したことにより、平成27年8月24日現在、参議院による採決が見送られている状況ですが、本改正案が成立した場合には、企業にとっての影響が大きいものとなりますので、今後の動向について注視する必要があります。
詳しくは、内閣官房のサイトをご参照ください。
垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方
本改正では、垂直的制限行為について、公正な競争を阻害する恐れがあるかどうかについて、様々な状況(例えば、ブランド間競争の状況、メーカーの市場における地位、流通業者の事業活動に及ぼす影響、流通業者の数や市場における地位など)が総合的に考慮され、加えて、垂直的制限行為には競争を促進する効果もある点も考慮して判断されるとしています。
なお、競争促進効果が認められ得る典型例として、いわゆる「フリーライダー問題」が解消される場合、サービスの統一性やサービスの質の標準化が図られる場合などが挙げられています。
問題となりやすい垂直的制限行為について、判断基準を明確にすることによって、制限が課される行為者(メーカーなど)に対して、ビジネスにおいて過度な萎縮効果をもたらすことがないように配慮された内容となっています。
※垂直的制限行為とは
メーカーが自社商品を取り扱う流通業者(卸売業者や小売業者など)の販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等の制限を行う行為のことをいいます。
まとめ
今回の改正によって、ガイドラインの内容がより明確になっていますので、ガイドラインに関連したビジネスをされている企業様は、改正内容についてご確認いただければと思います。
詳しくは、公正取引委員会のサイトをご参照ください。
- 1企業統治の在り方に関する改正の概要
 監査等委員会設置会社制度の新設
監査等委員会設置会社制度の新設 社外取締役及び社外監査役の要件が見直され、社外要件を満たさない取締役
社外取締役及び社外監査役の要件が見直され、社外要件を満たさない取締役
(業務執行取締役等を除く)及び監査役も責任限定契約の締結が可能となる 社外取締役が存在しない上場会社は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を
社外取締役が存在しない上場会社は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を
事業報告の内容とし、定時株主総会において当該理由の説明が必要となる 会計監査人の選任等に関する議案決定権限を取締役(会)から監査役(会)への変更
会計監査人の選任等に関する議案決定権限を取締役(会)から監査役(会)への変更 募集株式の発行(支配株主の異動を伴うもの、仮装払込みによるもの)への規制
募集株式の発行(支配株主の異動を伴うもの、仮装払込みによるもの)への規制
- 2親子会社に関する規律に係る改正の概要
 多重代表訴訟制度の新設
多重代表訴訟制度の新設 特定支配株主による株式売渡請求(キャッシュ・アウト)制度の新設
特定支配株主による株式売渡請求(キャッシュ・アウト)制度の新設 組織再編における株式買取請求手続の新設
組織再編における株式買取請求手続の新設 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設
詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設 自社及びその子会社から成る企業グループの内部統制システムの整備について、
自社及びその子会社から成る企業グループの内部統制システムの整備について、
会社法施行規則から会社法の規定に格上げ
まとめ
今回の改正による様々な新制度が導入され、役員・機関構成の見直しなどが必要となるケースもありますので、この機会に会社の将来像を見据えてご検討いただけると良いかと存じます。改正法の詳細については、法務省のサイトをご参照ください。
個人情報保護法における規定に関し、それぞれ取組の充実・強化を図ることを目的としています。
- 1第三者からの適正な取得の徹底(第17条)
・第三者から個人情報を取得する場合には、適法に入手されていること等を確認することが望ましい旨追記。
・適法に入手されていることが確認できない場合は、取引を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい旨追記。
- 2社内の安全管理措置の強化(第20条)
・外部からのサイバー攻撃対策の追加
・内部不正対策の組織的、物理的、技術的安全管理措置の項目の追加
- 3委託先等の監督の強化(第22条)
・内部不正対策の委託先の安全管理措置の確認、定期的な監査等の追加
・再委託先以降も同様の措置を行うことが望ましい旨を追記
- 4共同利用制度の趣旨の明確化(第23条)
・事業者が共同利用を円滑に実施するための共同利用者における責任等を追加
・共同利用者の範囲の明確化
- 5消費者等本人に対する分かりやすい説明のための参考事項の追記
個人情報保護法の改正案
情報通信技術の発達による環境の変化に伴い、個人情報の取扱いの見直しが検討されており、内閣官房は、個人情報保護法の改正案の原案を取りまとめ、今国会に提出する意向を示しています。これを受けて、個人情報関連の様々な分野におけるガイドラインも見直される可能性がありますので、企業様に関係のある分野のガイドラインの動向について注目いただければと思います。
経済産業省分野の個人情報保護ガイドラインの改正につきましては、以下のサイトをご参照ください。
- 1公表罪
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、性的な画像を不特定多数に提供し、又は公然と陳列する行為は「公表罪」にあたり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
- 2公表目的提供罪
①の行為をさせる目的で、性的な画像を提供する行為は「公表目的提供罪」にあたり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。
- 3プロバイダ責任制限法の特例(画像の削除)
プロバイダは、被害者からの画像削除の申出に対して、画像が権利侵害となるか判断できない場合、画像の発信者に削除への同意につき照会し、7日経過しても不同意の申出がない場合は削除できます。この法律の特例として、被害者からの画像削除の申出に迅速に対応するため、発信者からの申出期間を2日に短縮しました。
企業としての対応
万が一、会社の従業員が被害者又は加害者となった場合には、会社名を含む個人情報が特定され、広範囲に情報が拡散する可能性が考えられますので、従業員を守るためにも社内教育を通して啓蒙活動を行うことが予防策の一つと考えられます。
電子商取引及び情報財取引等に関する準則の改訂 (平成26年8月8日)
経済産業省は、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「本準則」)を平成26年8月8日に改訂しました。
電子商取引及び情報財取引等に関する準則とは、電子商取引及び情報財取引等おける法的問題点について、判例の蓄積等を待つのでは速やかには明確とならない法解釈を市場の要請に応じて明確化するとともに、既存の民法や関係法令の限界を明らかにして新たなルール形成のための指針として、経済産業省が平成14年3月に策定したものです。
本準則の主な改訂内容
- 1消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正
- 2未成年者による意思表示に関する論点の修正
- 3デジタルコンテンツに関する論点の追加
①インターネット上での提供等における法律問題
②デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用
③電子出版物の再配信を行う義務
④オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係
まとめ
本準則は、事業者や消費者を何ら拘束するものではありませんが、裁判上では影響力のある基準となり得ることから、今回の改訂におけるデジタルコンテンツの論点に関係のあるクライアント様は、その内容をご確認いただければと思います。詳細については、以下の経済産業省のサイトをご覧ください。
パーソナルデータの利活用に関する制度改正大網 (平成26年6月24日)
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)は、個人情報保護法(以下「法」といいます)の改正に向けて、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大網」を平成26年6月24日に公表しました。
背景として、情報通信技術が急速に発展したことから、個人情報の自由な利活用が許容されるかが不明確な「グレーゾーン」が発生・拡大し、保護すべき個人情報の範囲や事業者が遵守すべきルールがあいまいになってきたことを受けて、IT総合戦略本部において、法改正の検討がなされました。
主な内容
- 1本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等
個人データ等から「個人の特定性を低減したデータ」への加工と目的外利用や第三者提供の際の本人の同意の代わりとしての取扱いに関する規律を追加して定めます。
- 2基本的な制度の枠組みを補完する民間の自主的な取組の活用
時代と共に保護すべき個人情報の範囲などは変化するため、法律では、大枠を定め、具体的な内容は政省令、規則及びガイドラインにより対応し、これと併せて民間の自主規制ルールを活用することを図ります。
- 3第三者機関の体制整備等による実効性のある制度執行の確保
法令や民間の自主規制ルールをを実効性のあるものとして運用するため、独立した第三者機関の体制を整備します。
今後の見通し
平成26年7月24日で募集終了となったパブリックコメントに基づき、改正案が取りまとめられ、平成27年通常国会に提出される予定となっています。また政府は、ベネッセコーポレーションの顧客情報漏えい問題を受け、改正案に情報漏えい対策の強化を盛り込む方針も固めており、今後の動向に注目する必要があります。
景品表示法の一部改正 (平成26年6月6日成立)
食品表示等の不正事案の多発を受けて、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)当の一部を改正する等の法律」が平成26年6月6日に成立しました。施行日は、一部の規定を除き、公布の日(平成26年6月13日)から起算して6ヶ月を超えない範囲で政令に定める日となります。
景品表示法の主な改正内容
- 1業者のコンプライアンス体制(表示管理体制)の確立
事業者には、内閣総理大臣が公表する指針(本改正法の施行までに定められるものと思われます)に基づき、表示等の適正な管理のための必要な体制を確立する義務が課されました。また、内閣総理大臣は、事業者が確立した体制について指導、助言及び勧告を行うことができ、事業者が勧告に従わないときは、公表される可能性があります。
- 2情報提供・連携の確保
地域で活動する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、景表法の違反行為の差止請求権が認められている適格消費者団体に対して、不当表示等の情報提供ができるものとし、また、国、地方公共団体、又は国民生活センター等の関係者は、情報交換等により相互の密接な連携の確保を行うよう定められました。
- 3監視指導態勢の強化
不当表示への対応を迅速かつ的確に対処するため、消費者庁長官の権限について、調査権限を事業所管大臣等に委任できることとし、また、措置命令権限や合理的根拠の提出要求権限を都道府県知事に付与することができるとされました。
今後の見通し
平成26年6月10日現在、消費者庁は、本改正法の規制強化のため、不当表示に係る課徴金制度を導入する方針を決めており、今後の動向に注目する必要があります。
本改正法の詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。
消費者裁判手続特例法 (平成25年12月4日成立)
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「本法律」といいます。)が平成25年12月4日に成立しました。施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲で政令で定める日となります。
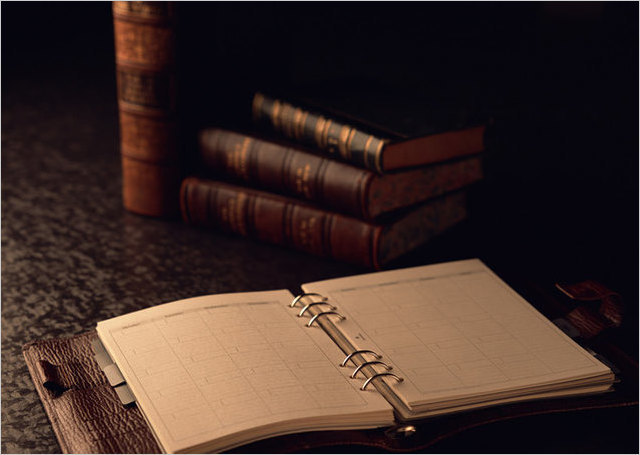
本法律の目的
近年多発している消費者被害において、事業者と消費者との情報の質及び量並びに交渉力の格差があることにより、消費者が自ら被害の回復を図ることが困難な状況にあることから、個々の消費者が、簡易・迅速に請求権を主張することができる新たな訴訟制度(以下「本制度」といいます。)が本法律により創設されました。
本制度の概要
本制度では、同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑み、消費者被害の集団的な回復を図るため、二段階型の手続となっています。
- 1一段階目の手続 (共通義務確認訴訟)
個々の消費者の利益を代弁できる適切な者に手続を追行させ、共通する原因により事業者が金銭の支払義務を負うか否かの判断が先行して確定されます。
- 2二段階目の手続 (対象債権の確定手続)
一段階目の手続で事業者が共通義務を負うことにつき確定された場合には、個々の消費者が、二段階目の手続に加入して、簡易な手続きによってそれぞれの債権の有無や金額が迅速に決定されます。
まとめ
本制度では、消費者契約に関して事業者に対する一定の金銭の支払請求権が生ずる事案を対象としていますので、クライアント様の事業内容が本制度の対象となり得るのかどうかをご確認いただく必要があります。
詳細につきましては、以下のサイトをご参照いただければと思います。
営業秘密管理指針の改訂 (平成25年8月16日公表)
経済産業省は、営業秘密管理指針を改訂し平成25年8月16日に公表しました。

改訂内容
人材を通じた技術流出の防止措置としての退職者との競業避止義務契約について、今までの裁判例に基づき、有効性が認められる可能性が高いポイントなどが本指針に盛り込まれ、また、それらの詳細について参考資料6にまとめられています。
競業避止義務契約の有効性
本指針では、競業避止義務契約の有効性について、実際の裁判例ではどのような判断がなされているかに言及しつつ以下の判断ポイントについて説明をしています。
※【2】~【6】については、【1】を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から判断をします。
- 1企業側の守るべき利益(包括的ではなく、具体的に存在していること)
- 2従業員の地位(企業が守るべき秘密情報との関わりが実質的にあるかどうか)
- 3地域的限定(業務の性質等に照らして合理的な絞込みがなされているかどうか)
- 4競業避止義務期間(1年以内⇒肯定的、2年⇒否定的[近時の事案])
- 5禁止される競業行為の範囲(業務内容や職種等について限定した規定⇒肯定的)
- 6代償措置(代償措置と呼べるものが何もない場合⇒否定的)
本指針の改訂に基づき、競業避止義務契約の導入・見直しが必要になると思われます。
ただ、判例自体は個別性が強いため、実際には、各クライアント様に合った契約条項をご検討いただく必要がありますので、この点につき、ご留意いただければと思います。
詳細は下記のサイトをご参照ください。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に関するガイドライン (平成25年10月1日)
消費税の引き上げにあたり、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「本法律」といいます。)が、平成25年10月1日に施行されました。また、本法律に関して、各省庁からガイドラインが公表されております。
消費税転嫁対策特別措置法について
本法律のポイントは以下の通りとなります。
- 1消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)の禁止
独占禁止法や下請法においても問題となり得るものですが、本法律では、規制対象となる企業や取引を大幅に拡大しておりますので、注意が必要です。公正取引委員会が公表しているガイドラインでは、運用方針などが示されています。
- 2消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止
全ての事業者が取締りの対象となっており、消費者庁が公表しているガイドラインでは、広告表示に関する考え方などについての説明がなされています。
- 3「総額表示」義務の緩和と「外税表示」・「税抜き価格の強調表示」の是認
消費者庁公表のガイドライン(【2】とは別のもの)及び財務省公表のガイドラインでは、価格の表示方法について、具体例を挙げながら説明がなされています。
- 4中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や表示方法を統一すること
(表示カルテル)が認められる
公正取引委員会が公表しているガイドライン(【1】と同じもの)では、どのような行為が問題となるのかなどについて具体的に示されています。
- 5国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行うこと
本法律の適用期限
本法律における特別措置の適用期限は、施行日から平成29年3月31日までとなりますので、その点につきましてご留意いただく必要がございます。
パーソナルデータの利用・流通に関する研究会における報告書
(平成25年6月12日公表)
総務省は、「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」において取りまとめられた報告書を平成25年6月12日に公表しました。

報告書の主な概要
ネットワーク上のパーソナルデータ(個人に関する情報)の利活用のルールが明確でないため、企業にとっては、どのような利活用が適正であるかの判断が困難であり、また、消費者にとっては、自己のパーソナルデータが適正に取り扱われ、プライバシー等が適切に保護されているかが不明確になっています。
このことから、総務省は、パーソナルデータを広範囲なものとして捉えて、パーソナルデータの利活用の基本理念及び原則を明確化した上で、具体的なルール(準則)を設定・運用していくことが必要であるとしています。
パーソナルデータ利活用の基本理念
- 1個人情報を含むパーソナルデータの保護は、主としてプライバシー保護のために行うものである。
- 2プライバシーの保護は、絶対的な価値ではなく、表現の自由、営業の自由などの他の価値との関係で相対的に判断されるべきものである。
基本理念を具体化したパーソナルデータ利活用の7つの原則
- 透明性の確保
- 本人の関与の機会の確保
- 取得の際の経緯(コンテキスト)の尊重
- 必要最小限の取得
- 適正な手段による取得
- 適切な安全管理措置
- プライバシー・バイ・デザイン(パーソナルデータを利用する者は、商品開発時などそのビジネスサイクルの全般にわたって、プライバシーの保護をデザインとしてあらかじめ組み込んでおくこと。)
詳細につきまして、総務省のサイトをご参照いただければと存じます。
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日)
法務省における法制審議会の民法部会は、平成25年2月26日に「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」をまとめました。

主な中間試案の項目
中間試案における提案内容や論点は、多岐(約300項目)にわたりますので、特にビジネスに重要と思われます項目を以下に挙げさせていただきます。
- 法定利率の見直し(現行の「年5%の固定制」から「1年毎に0.5%刻みの変動制」にすること、また、法改正時の法定利率は3%に引き下げること)
- 債務不履行による契約解除の要件の見直し(債務者の帰責事由要件の不要化)
- 保証人保護の方策の拡充(個人が保証人となる一定の類型の保証契約を一律無効とすること、保証人[個人]に対する契約締結時の説明義務・情報提供義務や契約締結後の主たる債務の履行状況に関する情報提供義務などを規定すること)
- 債権譲渡(債権譲渡特約の効力、対抗要件など)に関する見直し
- 契約交渉段階における規律(契約交渉不当破棄、情報提供義務など)の明文化
- 約款に関する規律(約款中の不意打ち条項は契約内容から除外されること、また、不当条項は無効とされることなど)の明文化
- 継続的契約の終了に関する特則(契約が継続されることを期待して取引を行っていた者の信頼を保護する趣旨の提案)
- 売買の瑕疵担保責任の見直し(「瑕疵」ではなく、「契約不適合」という概念を用いることとし、買主の履行追完請求権や代金減額請求権を認めることなど)
- ファイナンス・リース契約およびライセンス契約の規律の明文化(賃貸借に類似する契約と位置づけ、賃貸借の節に規定すること)
新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について
(案)の公表 (平成25年2月 特許庁)
特許庁は、「商標」に、動き、音などを新たに加える商標法改正案を2013年の国会に提出する方針であるとして、2月に、「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について(案)」と題する報告書案を公表しました。

背景
近年のデジタル技術の急速な進歩や事業のグローバル化に伴い、企業のブランド戦略に活用される「商標」の保護対象を広げることにより、企業の商品やサービスの販売戦略の多様化を促進させるべく、本法改正案が検討されています。
主な改正案の内容
日本の現行制度においては、「文字、図形、記号若しくは立体的形状もくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」したものが商標の保護対象とされていますが、本法改正案では、新たに「動き」「ホログラム」「輪郭のない色彩」「位置」「音」を商標の保護対象とする方針が示されています。
海外において、保護対象とされている「におい、味、触感」については、適切な制度運用が定まった段階で保護対象に追加できるように、検討するものとされ、本法改正案では見送りとなりました。
今後の対応
本法改正案による改正法が成立すると、
- 1企業の多様なブランドメッセージ発信手段の保護
- 2グローバル市場における有効な模倣品対策の拡充
- 3日本が加盟しているマドリッド協定議定書に基づく国際登録制度を利用した低廉・簡便な海外における権利取得
が可能となります。他方で、自社の商品やサービスについて、他社の音や色などの商標を侵害しているか否かについて検討する必要が出てきます。
詳細につきまして、以下の特許庁のサイトをご参照いただければと思います。
平成24年9月7日、法制審議会は「会社法制の見直しに関する要綱」をとりまとめ、法務大臣に答申しました。今後、その要綱内容が法務省と内閣法制局により条文化され、国会により会社法の改正が実現すると予想されます。
主な改正点
会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、【1】企業統治の在り方や【2】親子会社に関する規律等を見直しています。
- 1企業統治の在り方の見直し
社外取締役の機能を活用するために、監査・監督委員会設置会社制度(仮称)(監査役を置かず、取締役により構成される委員会が監査を行う会社の制度)が創設され、また、社外取締役等の要件が厳格化(親会社関係者・取締役等の近親者でないことを要件に追加)されます。
そして、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を監査役に付与することにより、会計監査人の独立性を強化しています。
- 2親子会社に関する規律等の見直し
親会社株主の保護として、多重代表訴訟制度(親会社の株主が子会社の取締役の責任を追及する訴訟)が創設され、また、組織再編等における株主の保護として、組織再編等の差止請求制度が拡充されます。
また、金融商品取引法との関係では、公開買付規制に違反した株主による議決権行使の差止請求制度が創設されます。
まとめ
今回の要綱では、上場会社にフォーカスを当てた改正内容となっております。
一方、非公開会社のみに関係する事項としまして、会計限定監査役(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定すること)を定める場合、今までは定款に定めるだけで足りたところ、改正により登記事項となり、すでに監査役に会計監査限定の定めを設けている会社は、登記手続き上の実務の対応が必要となりますので、その点につき、ご留意いただければと存じます。
詳しくは法務省のサイトをご参照ください。
スマートフォン プライバシー イニシアティブ (2012年8月7日公表)
総務省は、スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関する指針として「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」を2012年8月7日に公表しました。
指針のポイント
本指針では、スマートフォンをめぐるサービス提供に関係している事業者等に対して、以下のような利用者情報取扱指針が示されています。
- 1「個人情報」に該当する情報に関する基準の明確化
個人情報保護法上では、個人識別性の有無が「個人情報」該当性の要件とされていますが、具体的に何が「個人情報」にあたるかについての基準が不明確でした。
本指針は、この個人識別性の有無について、利用者が容易に変更できる情報であるか否か、という変更可能性を一つの基準として表にまとめており、何が「個人情報」に該当し得る情報であるかを具体的に説明しています。
- 2プライバシーポリシーの見直し
プライバシーポリシーにおける記載項目や表示方法などについて、何が適正であるか、具体的な例を挙げながら説明しています。
例えば、将来的な活用を見込んで利用目的の範囲を定めずに利用者情報を取得することは適切ではないとしたり、プライバシーポリシーの変更により、同意取得している事項の範囲を変更する場合、改めて同意取得を行うこととしています。

今後の対応
本指針では、スマートフォンを含むITサービスにおいて取得する利用者情報の取扱いについて、総務省の考え方が示されているため、IT関連の企業様は、本指針をご確認いただき、プライバシーポリシーの見直しをご検討いただくことが良いと思います。
詳細については、下記の総務省のサイトをご参照ください。
著作権法の一部を改正する法律案 (2012年6月20日成立)
第180回国会に提出された「著作権法の一部を改正する法律案」が2012年6月20日に成立しました。
主な改正内容
本法律案は、
- 1著作権等の制限規定を整備
デジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物の利用形態の多様化等への対応として、著作権等の制限規定を整備すること
- 2著作権等の技術的保護手段に係る規定を整備
著作物の違法利用・違法流通が常態化していることへの対応として、著作権等の技術的保護手段に係る規定を整備すること
を主な内容としています。
施行期日は、平成25年1月1日(技術的保護手段に係る規定等については平成24年10月1日)です。
ここでは、【1】著作権等の制限規定の整備についてご説明いたします。
著作権等の制限規定の整備
著作物の利用の円滑化のために、以下の著作物の一定の利用行為につき、著作権等の侵害にならないとする規定を設けています。
- 写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物(付随対象著作物)を当該創作に伴って複製又は翻案することを行うこと
- 許諾を得て又は裁定を受けて著作物を利用しようとするものが、利用に係る検討の過程において、必要と認められる限度で、著作物を利用すること
- 録音、録画その他の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合に、必要と認められる限度において当該著作物を利用すること
- 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための記録媒体への記録または翻案
今後の対応
今回の改正によって、従前より著作権の権利侵害の疑義が生じていた著作物の利用行為についての適法性が明確化されることになります。
詳しい内容については、下記の文部科学省のサイトをご参照いただければと思います。
不正競争防止法の一部を改正する法律 (2011年12月1日施行)
「不正競争防止法の一部を改正する法律」が2011年12月1日に施行されました。
主な改正内容として、
- 1営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
- 2アクセスコントロール回避装置に対する規制強化
があります。
ここでは、【1】についてご説明します。
営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備
営業秘密侵害罪について、被害企業が、刑事訴訟手続において営業秘密の内容が公になることを恐れて、告訴を躊躇する事態が生じていることにかんがみ、営業秘密の適切な保護を図るため、刑事訴訟の過程において営業秘密の内容を保護するための手続が設けられました。
営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続の内容として、被害企業等の申出がある場合、裁判所は、営業秘密の内容を秘匿し、別の呼称を用いることができ、また、公判期日外において、傍聴人なしで証人等の尋問及び被告人質問を行うことができるようになりました。

営業秘密管理指針の改訂
このような不正競争防止法の改正をうけて、営業秘密管理指針が改訂されました。
改訂された指針では、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続に関して、被害企業が自らの営業秘密を守るために、検察官に対してどのような協力を行えばよいかイメージしやすいように、刑事訴訟手続の一連の流れや秘匿の申出書等の記載例などが掲載されています。
ご興味のある企業様は、下記の経済産業省のサイトをご参照いただければと思います。
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上
の問題点及び留意事項 (2011年10月28日公表)
消費者庁から「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」が、平成23年10月28日に公表されました。

経緯
インターネットを活用した取引の大きな成長・発展に伴い、様々なトラブルや消費者被害が増加していることを受けて、消費者庁が平成23年3月11日に公表したインターネット消費者取引研究会報告書「インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組について」では、インターネット消費者取引に係る表示について事業者が守るべき事項を提示しています。
これを踏まえて、消費者庁は、同報告書の「検討事項として想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめました。
主な内容
インターネット消費者取引に新たなサービス類型(フリーミアム、口コミサイト、フラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラム、ドロップシッピング)が現れていることから、それらのサービス類型について、定義及び概要がまとめられ、景品表示法上の問題点、問題となる事例及び留意事項が示されています。
まとめ
ここでとりまとめられているのは、新たなサービス類型の「定義及び概要」に記載されているモデルを前提にしたものですので、具体的な表示が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとに判断されることになります。そこで、その点につきご留意いただく必要があります。
詳しくは下記の消費者庁サイトをご参照ください。
東京都暴力団排除条例 (2011年10月1日施行)
「東京都暴力団排除条例」が、平成23年10月1日に施行されました。今回の条例の施行により、全都道府県内で同種の条例が出揃いました。
条例の主な内容
この条例では、
- 「暴力団を恐れない」
- 「暴力団に金を出さない」
- 「暴力団を利用しない」
- 「暴力団と交際しない」
の4つを基本理念として、
- 1都、都民及び事業者の果たす役割
- 2暴力団排除に関する基本的施策
- 3事業者の暴力団関係者に対する利益供与の禁止
などについて定められています。
ここでは、【1】及び【3】についてご説明します。

事業者の果たす役割
契約締結に関する責務として、契約締結時に相手方が暴力団関係者でないことを確認し、契約締結時に、相手方が暴力団関係者と判明した場合、催告なく契約を解除できる旨の特約を定めるよう努めるものとされています。
事業者の暴力団関係者に対する利益供与の禁止
この条例では、事業者による暴力団の威力利用目的、又は暴力団の活動を助長する目的の利益供与等を禁止しています。事業者が条例違反をした場合、勧告や企業名の公表等の措置が取られます。
さらに、公安委員会は威力利用目的の利益供与をした事業者に対して、その行為の中止等の命令することができ、当該事業者がその命令に違反した場合における罰則規定も設けられています。
まとめ
今後、企業には暴力団をはじめとする反社会的勢力との一切の関係を排除することが求められます。まずは、企業様には、契約条項の改訂をしていただく必要があります。
東京都暴力団排除条例の詳しい内容に関しまして、下記にあります警視庁サイトにてご確認いただければと思います。
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を
改正する法律案 (2011年7月14日)
近年、コンピュータ・ウイルスによる攻撃やコンピュータ・ネットワークを悪用した犯罪など、サイバー犯罪は増加を続けています。
このような状況を受けて、コンピュータ・ウイルスを悪用した犯罪等を取り締まる刑法改正案「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が2011年6月17日に参議院本会議で可決・成立し、2011年7月14日に「不正指令電磁的記録作成罪」、いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を柱にした改正刑法が施行されました。
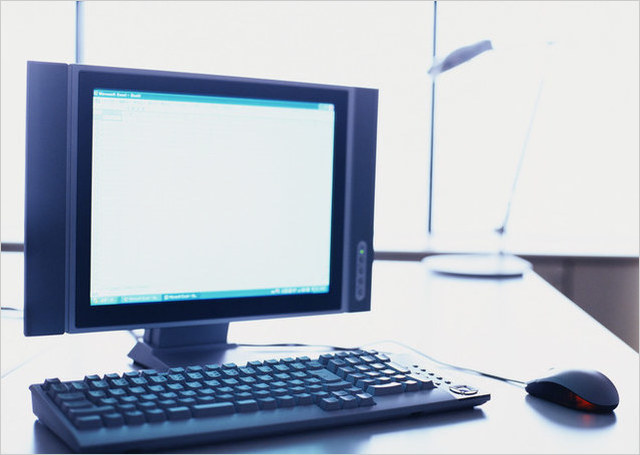
主な改正内容
ウイルス作成罪は、「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成、提供、供用、取得、保管する行為を処罰する」ことをいい、罰則は以下のとおりとなっています。
| 作成・提供・供用 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 取得・保管 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
また、これに合わせて、通信履歴の電磁的記録の保全要請の規定の整備がなされました。
検察官などは、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、通信事業者等に対し、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間(特に必要があり、延長する場合には、通じて60日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができることとしました。
まとめ
今回の改正について、捜査権の濫用によるプライバシー侵害を懸念する声も出ていますが、法務省のサイトではウイルス作成罪についての考え方を整理したものが公表されていますので、ご興味のある方は下記のサイトをご参照いただければと存じます。
当面の株主総会の運営について (平成23年4月28日)
経済産業省は、「当面の株主総会の運営について」と題するガイドラインを平成23年4月28日に公表しました。

ガイドラインの目的
今般の震災等の影響により、予定通り定時株主総会を開催することが困難であったり、たとえ開催した場合においても、株主の出席や事前の議決権行使等が困難になったりするおそれは完全には払拭できていません。
この状況を受けて、経済産業省は、株主総会の運営に係る法解釈および運用につき、参考となる指針が必要であるとして、「当面の株主総会の運営に関するタスクフォース」を開催し、本年6月末までに定時株主総会を開催する企業のためにガイドラインを取りまとめました。
ガイドラインの概要
当面の株主総会の運営について、以下の事項を、現状・問題点、考え方、およびガイドラインの項目に分けて説明をしています。
- 1招集通知等の早期ウェブ掲載
- 2電子化による株主向けの印刷物の削減
- 3招集通知発送後の招集事項の変更
- 4定時株主総会の運営
- 5定時株主総会の開催時期
まとめ
本ガイドラインは、本年6月末までに開催される定時株主総会の運営に役立てるための暫定的なガイドラインですが、経済産業省に寄せられる意見や実際の会社の取り組み状況等を踏まえて、本年7月以降に加筆修正が行われる予定です。
現時点では、被災地の復旧・復興状況、余震の発生状況や節電の影響等を完全に見極めることのできない状況ですので、7月以降に株主総会を開催する企業様は、今後の本ガイドラインの改訂に注目していただければ幸いです。
本ガイドラインの詳細につきまして、ご興味のある方は、ぜひご一読していただければと思います。
経済産業省は、「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」を平成23年4月1日に公表しました。

策定の背景
クラウドサービスにおいて、クラウド利用者は、情報セキュリティ対策が十分であるかどうか分からないという不安を持っていること、また、情報セキュリティ監査及び国際的な規格に準拠したJISQ27002(情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジメントの実践のための規範)ベースのセキュリティ管理をクラウド事業者に対して望んでいることが経済産業省の調査により明らかになっていました。
この調査結果を踏まえて、策定されたのが本ガイドラインになります。
※JISQ27002は、組織が自らのシステムを所有することを想定して作成されているため、その管理策のための手引きをそのままクラウドサービスに対して適用することはできません。
ガイドラインの目的
本ガイドラインを
- 1情報セキュリティ管理
- 2情報セキュリティ監査
に活用することにより、クラウド利用者とクラウド事業者における信頼関係の強化に役立てること、また、JISQ27002の管理策と管理目的に関して、クラウドサービス利用に着目した情報を提供することを目的としています。
ガイドラインの概要
本ガイドラインでは、JISQ27002に規定された管理目的の達成を目標として、組織がクラウドサービスを全面的に利用する究極的な状態を想定し、
- 1利用者が自ら行うべきこと
- 2クラウド事業者に対して求める必要のあること
- 3クラウドサービスの環境における情報セキュリティマネジメントの仕組み
について記載されています。
まとめ
本ガイドラインの活用によって、クラウド利用者及び事業者双方での管理や監査実施の円滑化が望めるほか、利用者と事業者間のコミュニケーションツールとしての活用も期待されています。詳細につきまして、ご興味のある方は、ぜひご一読いただければと思います。
東京地裁決定 (平成22年2月26日)
会社の不祥事が相次ぐ中、内部統制やコンプライアンス(法令遵守)の重要性が高まっています。そもそもコンプライアンスとは、大まかに分類すると、
- 1法律、条例、その他の政府の規制などの法規範
- 2就業規則、業務マニュアルなどの社内規範
- 3倫理・社会的な規範
の3つに分けられ、かなり広い概念となります。
今回は、上記【2】社内規範の違反について争われていた判例をご紹介します。
本件は、会社の倫理規定(コンプライアンス規定)などの違反があったという理由で諭旨退職の通告を受け、会社に退職願を提出し、退職した元社員が、この退職につき、諭旨退職事由がないのに会社の人事部長の脅迫により強制されたものであるから取り消す、また錯誤により誤って退職の意思表示したものであるから無効であるなどと主張をして、会社に対し社員としての仮の地位確認と賃金仮払いを求めた事案であり、裁判所は、元社員の申立てを却下しました。
裁判所は、
- 1元社員は、自己保身のために、社内の内部通報制度において、部下に対し元社員の上司についての虚偽の報告をするよう求め、さらに自らも虚偽の報告をして、会社諸規程・方針に違反したものということができ、特に、元社員は、会社のコンプライアンス調査を誤らせようとしたものと考えられるため、その違反の程度は重大というべきであり、
- 2元社員は、自宅待機中、他の社員との連絡を禁じる旨の命令に違反して、部下に何度も電話をかけていたことから、就業規則に違反したものとして、諭旨退職事由が認められ、また、元社員の退職の意思表示について、諭旨退職の事由の存在をふまえて、その自由意思に基づき有効にされたものと認められる
と判断しています。
今回の判例は、会社の倫理規定(コンプライアンス規定)違反を正面から認めて諭旨退職事由があるとしたものとして重要で、また上記の元社員の行動に関する事実認定において、会社側の調査のあり方が大きな判断材料のひとつとされており、たとえば、調査時の社員へのヒアリングなど、社内規定に基づく社内調査の進め方を検討するにあたり参考になると思われます。
ISO26000―社会的責任に関する手引き―(平成22年11月1日)
組織の社会的責任に関する国際規格である「ISO26000」が2010年11月1日に発行されました。ISOとは、International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称であり、国際的な標準規格を策定することで、各国市場間の生産品やサービスの円滑な流通促進に向けた環境整備を行っています。

ISO26000とは
相次ぐ企業の不祥事により投資家だけでなく経済社会全体に影響を及ぼしていることを背景に、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)に関する取組への関心が高まる中で、CSRの国際規格化として発行されたのがISO26000です。
また、ISO26000では、社会的責任は企業だけでなくすべてのステークホルダー(組織の決定や活動に利害関係を有するあらゆる者)を対象としているため、CSRの“C”(Corporate)をはずし、組織の社会的責任(SR:Social Responsibility)と称しています。
ISO26000の特徴として、ISO9000(品質マネジメントシステム)やISO14000(環境マネジメントシステム)と異なり、第三者認証を目的としないガイダンス(手引き)であることがあげられます。
すなわち、あらゆる種類の組織に適用可能な社会的責任の基準を定め、その手引きの提供を目的としているのです。
ISO26000の主な内容
ISO26000では、社会的責任につき、組織の決定および活動が社会および環境に及ぼす影響に対して、透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任であると定義しています。
また、社会的責任として、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重の7つの中核主題について解説がなされており、また、社会的責任を実現するためにどのように取り組むべきなのかなどについて解説しています。
今後の対応
ISO26000を利用することにより、社会的責任の国際的な基準を理解し、それぞれの組織に合わせた取り組みをしていくことが期待されています。
ISO/SR国内委員会では、中小企業が社会的責任に取り組むときの留意点や中小企業などにおける実践事例などをわかりやすく解説した「やさしい社会的責任」を発表しています。ベンチャー企業の方に参考になるものと思われますのでぜひご一読いただければと思います。
在宅ワークガイドライン

クラウドコンピューティング
「クラウドコンピューティング」とは、インターネット上に雲のように浮かぶ巨大なコンピュータ群を必要に応じて利用できるコンピュータの形態のことをいいます。
クラウドコンピューティングの低コスト・利便性が注目され、様々な企業がクラウド型の業務システムの開発を進めています。
クラウドコンピューティングで在宅ワーク
クラウドコンピューティングに注目が集まる中、人材サービス世界大手のアデコとNTT東日本は、インターネットを使った在宅人材サービスを年内に始めると発表しました。
業務内容は、在宅の主婦や高齢者をネットで結び、自宅でコールセンター業務などができるようにするものです。
クラウドシステムの開発・提供をNTT東日本が担当し、アデコは在宅勤務者の労働状況を遠隔で管理するというもので、3年以内に約1000人の在宅勤務者との契約を目指すというものです。
在宅ワークガイドライン
情報通信高度化やパソコン等情報通信機器の普及に伴い、アデコのケースのように、これらを活用して個人が在宅形態で働く上記のような住宅ワークが増加すると考えられます。
在宅ワークでは、それぞれの事情に合わせて柔軟に働くことができる反面、契約が一方的に
打ち切られたりするなど、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況です。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省から、在宅ワークに関する契約につき守るべき最低限の
ルールとして、「在宅多¥ワークの適正な実施のためのガイドライン」が発表されており、最近では、平成22年3月にアデコのような発注者が文書明示をすべき契約条件を追加するなどの改正が行われました。
ガイドラインには、在宅ワークの適正な実施のための解説つきの契約書雛形などが記載されていますので、在宅ワークに関する事業をお考えの方はご確認いただければと思います。
育児・介護休業法 (平成22年6月30日)
「育児・介護休業法」が平成22年6月30日から施行されます。
改正のポイント
- 1子育て中の短期時間勤務制度、及び所定外労働(残業)の免除の義務化
- 2子の看護休暇制度の拡充
- 3父親の育児休業の取得促進
- 4介護休暇の新設
企業様にとって関係があると思われます改正のポイント【3】について、以下で概略を記載させていただきます。
父親の育児休業の取得促進
- 1父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます。
- 2育児休業を取得した父親は、配偶者の出産後8週間以内の期間内であれば、特別の事情がなくても、育児休業を再度取得することができます。
- 3労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止します。
今後の対応
常時100人以下の労働者を雇用する企業は、【1】及び【4】については、「平成24年6月30日」まで適用が延期されていますが、改正に備え、就業規則等の見直しを検討していただく必要があります。
人事労務担当者のご担当者様は、下記にあります厚生労働省HPにて、ご確認いただければと思います。
営業管理指針(改訂版) (平成22年4月9日)
平成21年の不正競争防止法の改正(平成22年7月1日施行)を受けて、平成22年4月9日に経済産業省が『営業秘密管理指針(改訂版)』を公表しました。

営業秘密管理指針とは
事業者が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針として、経済産業省が策定・公表したものであり、不正競争防止法における営業秘密に関する説明や、営業秘密を保護するための管理の在り方について書かれています。
主な改訂内容
- 1改正不正競争防止法における処罰対象行為の明確化
処罰対象となる行為類型等を具体的な事例をあげて明らかにしています。
- 2事業者の実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の提示
営業秘密としての法的保護を受けるためには、事業規模や情報の性質等に応じた合理性のある秘密管理を行うことで足りることを明確にするとともに、営業秘密を認められ得るための管理方法と、漏えいリスクを最小化するための高度な管理方法とを分けて具体的に列挙しています。
- 3中小企業等における管理体制の導入手順例や参照ツールの提示
主に中小企業を対象として、適切な管理体制を構築するための導入手順例を紹介するとともに、営業秘密管理チェックシートや各種契約書の参考例などの参照ツールを提示しています。
まとめ
今回の改訂により、不正競争防止法上の営業秘密としての保護を受けることができるようにするための適切な管理方法がより明確になりました。
『営業秘密管理指針(改訂)』の詳細につきましてご興味のある企業様は、下記の経済産業省のサイトをご参照いただければと思います。
最高裁判所第一小法廷判決 (平成22年4月8日)

インターネットの掲示板に名誉を傷つけられるような書き込みをされた会社とその社長らが、プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)に基づき、書き込みに利用された接続業者「NTTドコモ」に発信者の契約者情報を開示するように求めた事案について、平成22年4月8日に最高裁判所第一小法廷でNTTドコモ側の上告が棄却され、同社長らのNTTドコモへの開示請求が認められました。
接続業者であるNTTドコモがプロバイダ責任制限法に規定されている開示請求の対象(「特定電気通信役務提供者」:レンタルサーバなどのように“不特定”の者によって受信されることを目的として通信を媒介している業者)に該当するかどうかが争点とされており、最高裁判所は、不特定の者に受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する接続業者は開示請求の対象になると判断しました。
プロバイダ責任制限法の規定上、“特定”のコンテンツプロバイダ(例 レンタルサーバなど)のために通信を媒介している接続業者は、開示請求の対象に該当しないとするNTTドコモ側の主張に対して、接続業者のみが発信者の個人情報等を保有していることが少なくないという公知の事実にかんがみ、コンテンツプロバイダだけでなく接続業者にも開示責任を負わせるべきであるというものです。
同種訴訟で地裁・高裁段階では、開示請求が認められるケースが多かったのですが、最高裁の判断は今回が初めてとなり、今後、この判断が開示請求の基準とされると思われます。
労働基準法の一部を改正する法律 (平成22年4月1日)
「労働基準法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点
- 1労使協定による割増賃金引上げなどの努力義務
- 2法定割増賃金率の引上げ
- 3年次有給休暇の時間単位付与
ここでは、改正点【3】について、以下で概略を記載させていただきます。
年次有給休暇の時間単位付与
現行では、日単位又は半日単位で年次有給休暇を与えることができるとされていますが、改正後は、事業場で労使協定を結べば、1年のうち5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることもできるようになります。
労使協定で定める事項
- 1時間単位年休の対象労働者の範囲
- 2時間単位年休の日数
- 3時間単位年休1日の時間数
- 41時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
留意点
今回の改正に伴い、給与体系等の見直しを検討していただく必要があります。例えば、年次有給休暇の時間単位取得を可能とさせる場合、就業規則の改正や労使協定の締結の準備が必要となります。
各企業様によって改正労働基準法の適用の範囲が異なる場合もございますので、人事労務のご担当者様は、下記にあります厚生労働省HPにて、ご確認いただければと存じます。
東京都千代田区の弁護士事務所「フランテック法律事務所」は、IPOを目指すベンチャー企業さま、新興市場に上場している企業さま、フランチャイズあるいはIT系の中小企業さま、ソーシャルメディアに関心のある企業さまの法律業務を中心にお手伝しております。
経験豊富な弁護士が親切・丁寧に相談にのりますので、お気軽にご相談ください。
労務問題にお困りの企業さまには社会保険労務士と共にご対応いたします。

受付時間:9:30~18:30(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)、池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営については、
担当:金井(かない)
メールでのお問合せ・ご相談の予約
お問合せ・相談予約
受付時間:9:30~18:30
(土日祝祭日は除く)
担当:藤井(ふじい)または池松(いけまつ)
スポーツジム・フィットネスクラブ経営について
担当:金井(かない)
メールは24時間受付
事務所概要
代表弁護士 金井 高志
弁護士 藤井 直芳
弁護士 池松 慧
フランテック法律事務所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目1-5 マストライフ神田錦町305



